ディープテック起業のリアルと未来展望!UntroD Capital Japan株式会社代表永田氏が語る成功の鍵とは?

「ディープテック分野で起業したいけれど、何から始めればいいのだろう…」 「日本の技術で世界と戦えるのか不安…」 「研究開発と事業化のギャップをどう埋めればいいのか…」
そんな疑問や不安を抱えるあなたへ。
本記事では、先日開催されたセミナー「Out of Bounds for Deeptech for Entrepreneurs 第1回セミナー」において登壇された、UntroD Capital Japan株式会社代表であり、ユーグレナのCEOも務められた永田暁彦氏が語るディープテック起業のリアルな視点や、成功へのヒントといった動画のエッセンスを凝縮して記載します。
この記事を読めば、ディープテック起業への第一歩を踏み出す勇気と、具体的な道筋が見えてくるはず。そして、さらに詳しい内容はぜひ動画本編でご確認ください!
この記事のポイント
- 永田氏が語る、ディープテックのリアルと成功戦略
- グローバル市場で勝つための視点と日本の強みとは?
- 研究者と経営人材の理想的な関係性
【永田暁彦氏が語るディープテックの現在と未来】
注目のディープテック領域と市場動向
- 直近の注目トレンド:
- 半導体関連の基礎技術。
- 防衛・デュアルユース(宇宙・防衛領域への政府支出増が背景)。
- デュアルユース分野の可能性: 安全保障の観点に加え、日本のユニークな立ち位置を活かしたグローバル展開に期待。
ディープテックでグローバルに戦う意義
- Go Globalが前提: 縮小する国内市場ではなく、成長するグローバルマーケットでの挑戦が不可欠。
- 非言語的テクノロジーの強み: 言語の壁を超え、技術力で世界市場を獲得するポテンシャルが重要。
- 日本の強み:
- 発酵技術・微生物分野: 食品業界大手企業など、世界で成功している企業多数。
- 有機化学分野: 創薬分野など、世界で戦える技術シーズが豊富。
研究開発と事業化のギャップをどう埋めるか
- 経営人材に求められる技術理解の深度:
- 研究を完璧に理解・実行できる必要はない。
- 技術の本質を理解し、投資判断や外部への説明責任を果たせるレベルが重要。
- 技術領域や難易度によって求められる理解度は異なる。
- 経営人材の資質:
- 特定技術の経験よりも、分析・読解・解析・理解し、言語化して判断するジェネラルな能力が必要。
- ポテンシャルを重視。
ディープテックで起業する意義
- マーケットの大きさ: グローバル市場を狙えるため、成功時の企業規模が大きくなる。投資家からの資金調達もしやすい。
- 「誰もできない」という武器: 独自技術は強力な競争優位性となる。
- 例:ユーグレナにおけるミドリムシ技術。
- 技術に固執せず、より良いものがあれば転換する柔軟性も必要。
- 社会課題解決への貢献(ディープイシューの解決): ディープテックは、人命救助、貧困問題、エネルギー問題など根深い課題の解決に貢献できるという大義がある。
経営人材が技術を選ぶには?
- 大学の産学連携やVCとの接点: EIR(客員起業家)制度などを活用し、プロダクトアウト型の技術シーズに触れる。
- 自ら技術を探す: 課題意識に基づき、大学などに足を運び、有望な技術を発掘する。
- サーチファンド型: 大きな課題を定義し、それを解決できる技術を探索する。
ディープテック起業家に求められるマインドセット
- 技術への固執からの脱却: 研究成果を武器にしつつも、研究の遅延や失敗を会社全体の責任にせず、柔軟に対応する。
- 課題解決へのコミットメント: 「どの技術を使うか」ではなく、「どんな課題を解決し、どんな成果を出すか」に軸足を置く。
- 研究開発と事業開発のバランス: R&Dのうち、リサーチ(R)よりもデベロップメント(D)に比重を置く意識。社会実装へのコミット。
創業初期における重要な意思決定
- 「誰を仲間にするか」: 能力よりも、創業者のビジョンに共感しコミットしてくれる仲間が重要。創業初期は役割分担よりもチーム全体の熱量が鍵。
- リアルテックファンドでは3人以上のチームに投資している。
- 創業初期のチームに必要な要素: コミットメント、心理的安全性。
ディープテックにおける投資家との付き合い方
- ITサービスとの違い: 最初の売上が上がるまでの期間が長い。この点を理解してくれる投資家との連携が重要。
- 研究の遅延はつきもの: 研究開発の進捗に一喜一憂せず、長期的な視点でのサポートが求められる。
資金調達戦略と成長戦略
- 政府支援の活用: 日本のディープテックスタートアップへの政府支援は手厚い。NEDOなどのプログラムを熟知し、活用する。
- エクイティ調達とのバランス: 必要以上のエクイティ調達を避け、ステップバイステップでの成長を目指す。
- キャッシュカウの重要性(永田氏の考え):
- 最終製品完成までの期間が長い場合、その過程で生み出せる技術や製品で収益を確保することも一案。
- エクイティ調達環境の変動リスクへの対応。
- 企業としてのバリューチェーン構築の早期経験。
- ただし、VCの方針によって考え方は異なるため、相談が重要。
日本のディープテックエコシステム活性化に必要なこと
- M&Aのバイサイド(買い手)の多様化: 大企業だけでなく、成長したディープテックスタートアップがM&Aの買い手となることが重要。
- スタートアップらしい文化を持つ企業が、次の受け皿となる好循環を生む。
いかがでしたでしょうか?
より詳細な内容や、セミナーの熱気を感じたい方は、ぜひ以下のリンクから動画本編をご覧ください!
[動画視聴はこちらから!]
ON&BOARD TIMES編集部
ON&BOARD TIMES編集部


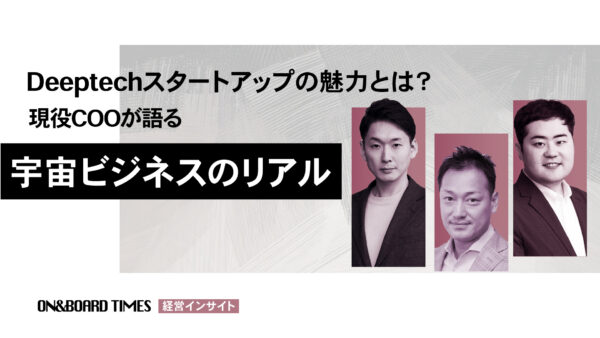

-600x338.jpg)

