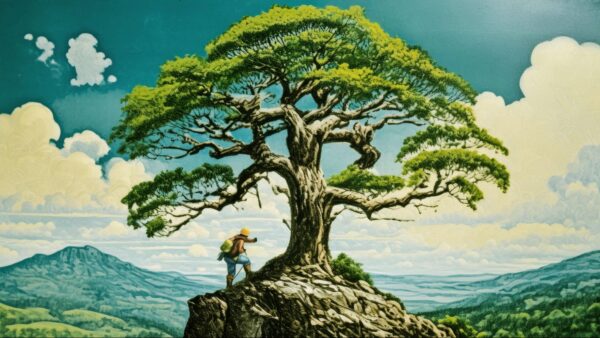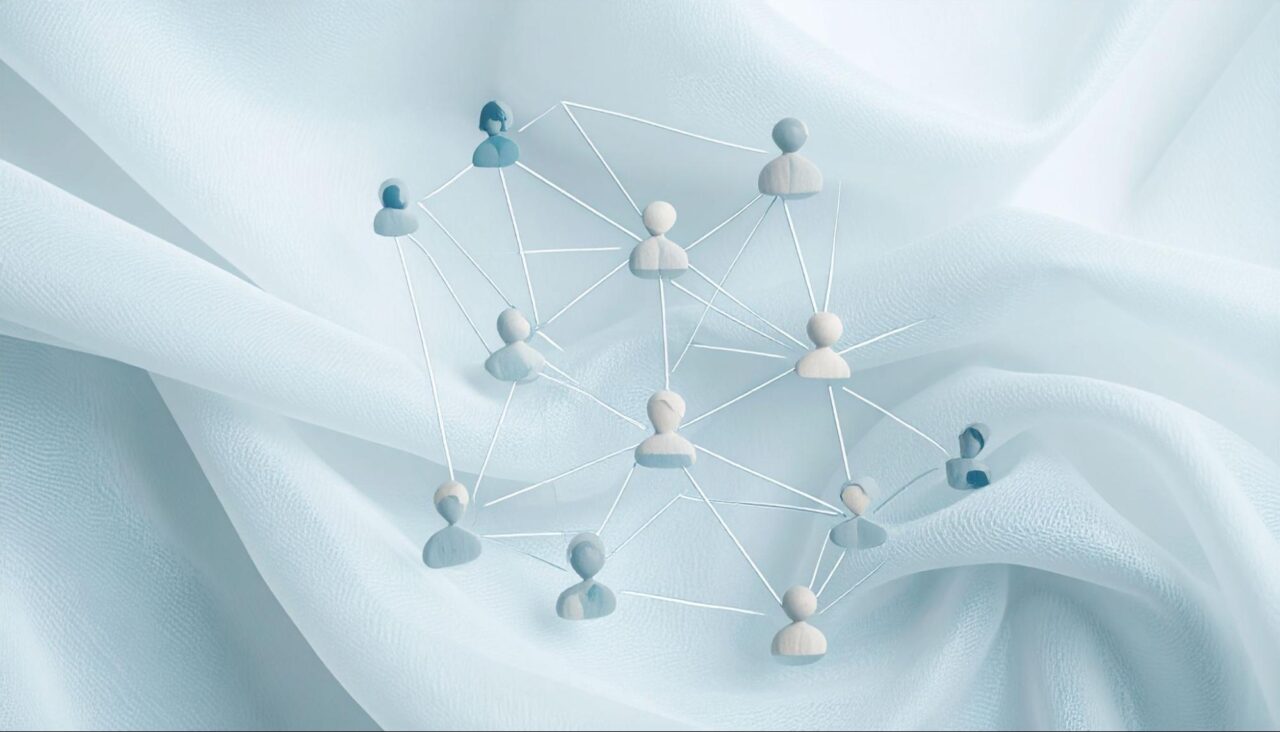
スタートアップの世界で、ひときわ大きな企業になりうる可能性を秘めているのが「プラットフォームビジネス」です。売り手と買い手、あるいはユーザー同士といった複数のグループを繋ぐことで価値を創出し、社会インフラにまでなるこのビジネスモデルは、多くの起業家にとって魅力的に映ります。
しかし、その成功の道のりは簡単ではありません。プラットフォームビジネスが競争優位性を築くためには、どのような戦略と視点が求められるのでしょうか。
目次
・プラットフォームビジネスの本質と「ネットワーク効果」
・戦略の分かれ道:「売り手」と「買い手」、どちらから集めるか?
・ケーススタディ:タイミーはなぜ勝てたのか
プラットフォームビジネスの本質と「ネットワーク効果」
プラットフォームビジネスを定義する上で最も重要な概念が「ネットワーク効果」です。これは、参加者が増えれば増えるほど、そのサービスの利便性や価値が高まる現象を指します。
例えばフリマアプリでは、売り手(出品者)が増えれば買い手(購入者)にとって商品の選択肢が増えます。また、買い手が増えると、売り手にとってさらに魅力的な場になります。この「参加者が参加者を呼ぶ」という好循環を生み出すことが、プラットフォーム成長のエンジンとなります。
しかし、ビジネスの立ち上げは、このネットワーク効果が働きません。「売り手がいないから買い手が来ない、買い手がいないから売り手も来ない」という、いわゆる「ニワトリとタマゴ問題」は、すべてのプラットフォーマーが直面する最大の壁です。

>Unsplash/Daniel Tuttle
最大の壁「ニワトリとタマゴ問題」をどう越えるか
この難問を、過去の成功企業はどのように乗り越えてきたのでしょうか。鍵となるのは、ネットワーク効果が働かない初期段階でもユーザーを惹きつけられる「単独での価値」を提供することです。
- Instagramの事例:今でこそ巨大SNSですが、初期は高機能な「写真フィルターアプリ」としてスタートしました。SNS機能がなくても、写真を綺麗に加工できるという単独の価値でユーザーを獲得しながら、プラットフォーム化を進めました。
- LINEの事例:LINEも当初、「無料通話アプリ」という分かりやすい便益を打ち出しました。通話料を節約したいというユーザーを集めながら、チャットを軸としたプラットフォームへと進化させました。
このように、まずは熱狂的な初期ユーザーを獲得できるキラー機能やサービスを磨き上げ、トラクションを築くことが、プラットフォーム化への第一歩となります。このフェーズではフリーミアムモデル(基本は無料で一部機能を使う場合などは有料にする)を採用することも多く、ある程度の先行投資に耐えられる資金調達力が不可欠です。
戦略の分かれ道:「売り手」と「買い手」、どちらから集めるか?
では、プラットフォームの両サイドにいるユーザーのうち、どちらを先に集めるべきなのでしょうか。
一般的には「獲得難易度が高い方から攻める」のが定石とされています。例えば、人手不足が深刻なアルバイト市場では、企業よりも「働き手」を見つけることの方が困難です。そのため、多くのサービスはまず魅力的な条件を提示して働き手を集めることに注力します。働き手のプールが確保できれば、人を探している企業は自然と集まってくるからです。
一方で、リクルートが得意とするようなBtoCのマッチングプラットフォームでは、まずB(企業)側を徹底的に集め、「ここに来れば選択肢が豊富にある」という状況を作ることで、C(消費者)を引きつける戦略が有効です。

>Unsplash/Dylan Gillis
ただし、この戦略は常に万能ではありません。例えば飲食店の予約サイトでは、掲載店舗数の多さよりも、本当に美味しい人気店が掲載されているかどうかがユーザーの満足度を左右します。この場合、KPIは加盟店数ではなく、上位人気店の掲載率となり、アプローチが全く異なります。
事業領域の特性を見極め、ネットワーク効果を最大化するために「誰を最初に集めるべきか」を戦略的に考える必要があります。
ケーススタディ:タイミーはなぜ勝てたのか
近年、上場して大きな注目を集めた「タイミー」は、プラットフォーム戦略を考える上で非常に示唆に富んでいます。なぜ、大手人材企業がひしめく市場で急成長できたのでしょうか。
1つは、働き手にとって「即日で給料がもらえる」という、既存のアルバイトにはない強力な価値を提供した点です。これにより、すぐにお金が必要なユーザーを惹きつけました。
もう1つは、大手企業側の「構造的な参入障壁」です。既存の人材紹介ビジネスで高い手数料を得ている大手にとって、単価の低い単発・短期バイト市場への参入は、自社ビジネスとのカニバリゼーション(共食い)を引き起こす懸念がありました。
タイミーは、その大手のジレンマによって生まれた時間的猶予を活かして先行投資を続け、ネットワーク効果を確立することに成功したのです。これは、かつてヤフオクが存在する中でメルカリが急成長した構図にも似ています。
プラットフォームビジネスは、単に良いアイデアだけでは成功しません。市場の特性を深く理解した上で、初期ユーザーをどう獲得し、ネットワーク効果のエンジンを回すのかこそが、競争優位性の源泉となるのです。
ON&BOARD TIMES編集部
ON&BOARD TIMES編集部