インターステラテクノロジズ熱田COOが語る、宇宙ビジネスのリアルと日本におけるDeep Techの可能性(後編)
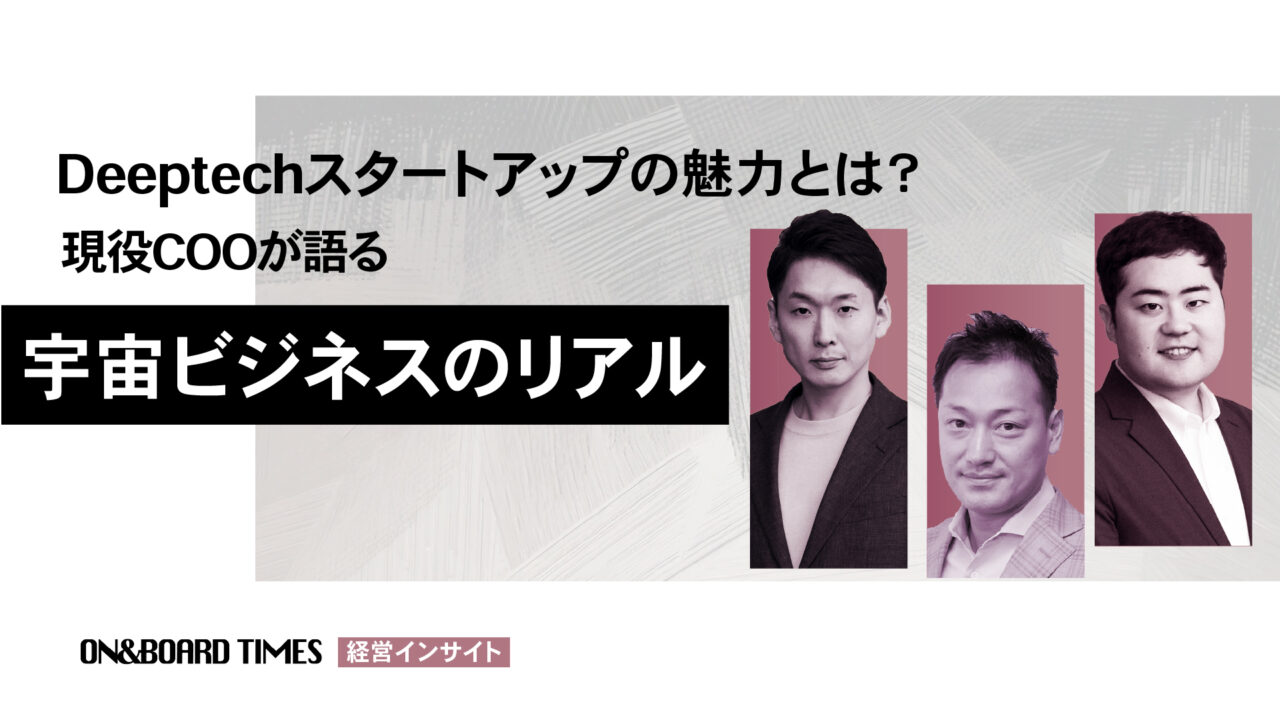
【目次】
- ディープテックスタートアップの資金調達戦略
- PMFへの長い道のりとモチベーション維持
- 組織文化とチームビルディングの重要性
- ディープテック領域で起業を目指す方へのメッセージ
【本文】
インターステラテクノロジズのCOO熱田氏へのインタビュー後編では、ディープテック企業特有の資金調達の課題、PMF達成への道のり、そしてチームビルディングと組織文化の重要性に迫ります。最後に、これからディープテック領域での起業を目指す方々への熱いメッセージをいただきました。
— 研究開発型のディープテックスタートアップにおける資金調達の課題とその対応について教えてください。
熱田:資金調達は一言で言えば「大変」です。当社もディープテックスタートアップとして、大規模な資金調達が必要となります。
日本独自の課題というわけではありませんが、宇宙領域ではアメリカや中国と比較されることが多く、日本のVCの拠出額は欧米と比べると大きくないのが実情です。また、VCにはファンドの償還期間という制約があるため、実績を出すジレンマも存在します。
このような状況において、ディープテックスタートアップにとって、まずは政府補助金の活用が非常に重要だと考えています。文部科学省のSBIRがこれに当たりますが、この補助金を活用し、まずはプロダクトのMVP(Minimum Viable Product)を作るための資金を確保します。
次に重要になるのが、事業会社とのシナジーを組み合わせた資金調達です。事業会社はディープポケットであり、VC以上に大きな金額を投資できる可能性があります。トヨタグループのウーブン・バイ・トヨタからの出資はまさにその一例です。ものづくりの文脈でシナジーを生み出すなど、事業会社に「本当に売り込める」シナリオをしっかりと描くことが重要です。
ファイナンス面では、政府補助金は営業外収益に、事業会社からの出資はエクイティになります。ディープテックの難しい点の一つは、デット(融資)が引きにくいことです。特に伝統的な金融機関との相性はあまり良くありません。しかし、政府との契約を獲得するなど、デットのロジックを金融機関に合わせて組み立てることで、融資を受けることも可能です。このように、補助金、エクイティ、デットを組み合わせる複雑な資金調達戦略が必要となります。
政府もディープテック領域の企業価値向上に注力する動きを見せています。そのため、ディープテックでの起業を考えるなら、政府の方針と合致しているか、あるいは政府にどう働きかけるかを探っていくと良いでしょう。

提供:インターステラテクノロジズ株式会社
— ディープテックではPMF(プロダクト・マーケット・フィット)までの道のりが長いと聞きます。社員のモチベーションを維持しながら、長期的なプロジェクトを進める上で意識していることは何ですか?
熱田:おっしゃる通り、ディープテックのPMFは非常に長い期間を要します。
PMFのKPI(目標)設定において、私が重視しているのは「高すぎない目標を立てる」ことです。ただし、この「高すぎない」目標も、外部に対してアピールできる材料である必要があります。政府へのアピール(具体的な成果を示す)と、投資家へのアピール(夢やビジョンを語る)は異なります。特に、政府や事業会社から資金を引き出すためには、単なる夢物語だけでなく、「このテクノロジーが現在のビジネスモデルをどう変えるのか」といった具体的なストーリーが必要です。エンジニアと経営陣が連携し、資金調達の視点も踏まえて研究開発を進めることが非常に難しい点です。
社内では、目標がまとまらないことが往々にしてあります。だからこそ、経営陣は一つの目標に向かって社員を動かすための設計をしなければなりません。個人のKPIまで具体的に落とし込み、「いつまでに何をやり切るか」を明確にすることが重要です。
また、「小さな目標を積み上げていく」ことが、大きな目標に向けて組織を動かす上で効果的です。スタートアップである以上、外部には「こんなことができる」という夢物語を見せる必要もありますが、内部では小さな目標達成を「素晴らしい成果」として評価し、社員のモチベーションを高めるようなバランス感覚が求められます。
長期プロジェクトのモチベーション維持に関しては、以下の点を意識しています。
- 全社集会での目標共有:定期的に全社集会を開き、年間の目標を明確に伝え、それがブレないように常に共有しています。各グループや領域のKPIも、この全社目標から細分化されます。
- PDCAサイクルの徹底:チーム内では「何が足りなかったか」「なぜこの結果になったのか」といったPDCAを徹底的に回します。
- 目標設定の柔軟性:スタートアップは外部・内部環境の変化によって、目標がドラスティックに変わることが頻繁にあるので、いかに早く目標やKPIを柔軟に変更できるかが非常に重要です。
- 「やらないこと」を決める:やりたいことは山ほどありますが、変化がある中で全てを追うことはできません。「これをやらない」と明確に決めることで、浮いたリソースを本当にやるべきことに一気に投入でき、スピード感を持って大手企業との差を生み出すことができます。
- シンプルな意思決定:複雑な状況でも、物事をシンプルに考えることを意識しています。まず試してみて、できたら次に進む、という形で、KPIも分かりやすくシンプルに設定することが、長期的な開発が必要な領域でも重要です。

提供:インターステラテクノロジズ株式会社
— 貴社におけるチームビルディングや組織文化において、特に意識されていることはありますか?
熱田:現在、当社は250名弱の組織ですが、チームビルディングや組織文化を形成する上で、VALUE(価値観)の設定と浸透を非常に重視しています。
当社のVALUEは現在4つあります(2025年7月時点)。
- 「やり切る」
- 「学び」
- 「全体志向」
- 「尊重」
これらのVALUEは、日々の業務レベルで実際に使われるように意識しています。例えば、開発がうまくいかない時や、顧客開拓が進まない時に、「このVALUEが達成できていないからではないか」と議論の基準にしたり、チームメンバーが悩んでいる時に「このVALUEが足りていないのでは」と助言したりします。
組織が100人の壁を越え、さらに大きくなると、VALUEが日々の行動変容に落とし込まれ、メンバー全員が活用できる状態になることが非常に重要です。これは宗教的と聞こえるかもしれませんが、組織が大きくなるほど、経営陣が「拠り所」となり、その思想をメンバーが次のメンバーへと伝えていくことで、カルチャーとして定着していきます。
ディープテック領域は、重厚長大で時間もかかるため、目に見えにくい部分でも強いコミットメントが求められます。だからこそ、そうした組織文化を共有し、浸透させていくことが、通常のビジネス以上に重要になると感じています。ディープテックは先行投資が大きく、研究開発にリスクが伴うため、社会インフラに実装されうるものには、やはり組織的な強い結びつきが必要となるでしょう。
— 最後に、これからディープテック領域での起業を目指す方や、創業を考えている方へのメッセージをお願いします。
熱田:ディープテック領域を活性化させるためには、ざっくり3つのポイントがあると考えています。
- テクノロジー:
- これは理系人材の確保、ひいては教育のあり方に繋がります。中国のように国策として理系人材を大量に輩出する国もあり、かつては日本が先行していた宇宙分野でも、今や中国ははるかに先を行っています。政府がテクノロジーを生み出す仕組みを整える必要があるでしょう。
- 一方で、VCは技術のシード(種)を発掘するのに長けているため、VCは引き続きその役割に注力すべきです。
- 資金需要:
- 初期段階の研究開発(POCなど)には、政府支援が不可欠です。
- しかし、ある程度事業化が見えてきた段階では、事業会社とのシナジーをスタートアップ自身が作り出す必要があります。いつまでも国の補助金に依存していては成長できません。事業会社、特に商社のような大規模な企業は大きな余力を持っており、VC以上に大規模な資金を投じることが可能です。事業会社には、もっと積極的にディープテック領域に投資してもらいたいと考えています。
- 事業化:
- ディープテックは「テクノロジー・ドリブン」になりがちで、その結果、研究開発だけで終わってしまう可能性があります。
- 顧客目線に立ち、実際に使われるサービスまで落とし込める「実行力」のある組織を築くことが鍵です。
- 私の経験からすると、商社出身の人材はこの事業化、特に「バイタリティを持って顧客を回り、テクノロジーをビジネスに繋ぐ」といった点が得意な傾向があると思います。時差ボケも気にせず動き回れるような体力がある人が、テクノロジーと顧客を繋ぐ役割を担うのに向いているかもしれません。
ディープテックは、資金調達、研究開発、マーケティングといった多岐にわたる要素を、非常に長い期間にわたって同時に進める必要があります。そのため、多様なステークホルダーとコミュニケーションを取りながら、長く走り続けられる人材が求められます。
しかし、世の中への貢献、産業構造の根底からの変革といったチャンスが本当に現実的にある領域だと私は確信しています。ぜひ恐れずにチャレンジしてほしいと思います。

提供:インターステラテクノロジズ株式会社
ON&BOARDでは、「Out Of BOUNDS for Deeptech Entrepreneurs」を通じて、ディープテック分野での創業を目指す方々へ、研究者・経営者のマッチング、資金調達、最先端ネットワーク、そして柔軟な参加体制で包括的に支援するプログラムを運営しています。
応募は通年受け付けていますので、Deeptech領域への挑戦にご興味のある方は、是非リンクからのご応募ください!
東京都出身。2009年三菱商事に入社。防衛・自動車関連のトレーディング業務、在インドネシア自動車販社における商品企画・販売のOperation主導、本社投資委員会における多数の投資・事業再生・撤退案件の稟議、自動車事業本部の戦略立案等、幅広い業務に従事。
商社での業務を通じて日本の産業競争力の変化を目の当たりする中、「日本発のイノベーション創出により直接的に関わりたい」との思いから、ON&BOARD創業に参画。
一橋大学法学部卒(在学中、英国Warwick大学Politics & International Studies留学)。





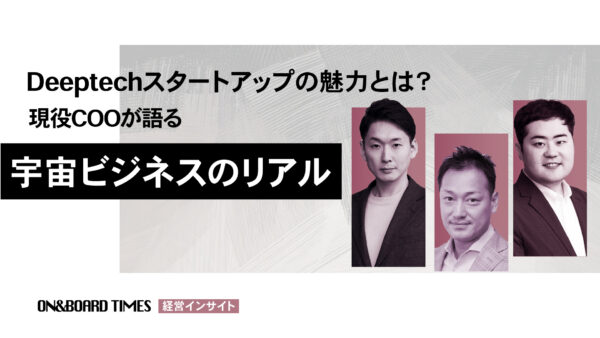
-600x338.jpg)

