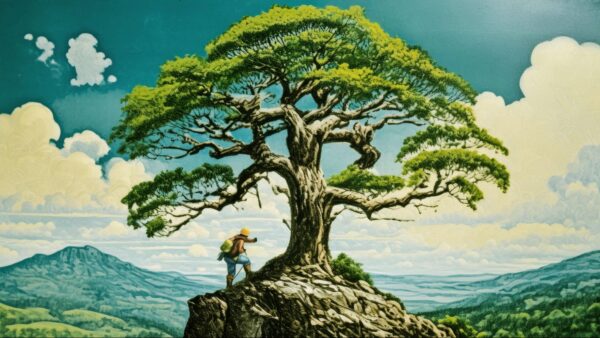福利厚生は大企業が提供する制度、というイメージが強いかもしれません。
しかし、スタートアップにおいても最適な福利厚生制度を構築できると、採用力の強化や社員のエンゲージメント向上に直結します。
事業が成長し人材が多様化するほど、その重要性は増していき、会社独自のカルチャーを形づくる武器にもなります。
目次
・なぜスタートアップに福利厚生が必要なのか
・社員が喜ぶ制度を作ろう
・成果・企業成長につながる仕組みを
なぜスタートアップに福利厚生が必要なのか
創業初期は福利厚生に意識が向く企業は少ないのが現状です。しかし、事業が成長し、多様な人材が加わるようになると、福利厚生制度の必要性も浮上してきます。
特に大企業で勤務していた人は、福利厚生制度がある前提で働いてきたため、制度の有無が採用・定着率に影響することもあります。
せっかく制度をつくるなら、本当にメンバーが喜ぶ制度を作るべきですし、他社と異なるものを提供できると、採用面談時にユニークなカルチャーとしてもアピールすることができます。
- 福利厚生制度が未整備であることを逆手にとり、ゼロからみんなでつくることで、一体感を生むチャンスにも
- 組織文化に沿った制度をつくることで、単なる採用施策にとどまらず、独自性を企業カルチャーとして語れるものに

>Unsplash/Priscilla Du Preez 🇨🇦
社員が喜ぶ制度を作ろう
スタートアップでよく見かける福利厚生といえば、社員同士や候補者とのランチ代の補助や家賃補助です。
やはり最もインパクトが大きいものは家賃補助です。
前職から年収を下げてスタートアップに転職するケースもあることから、家賃補助で手取りを実質増やすことができるのは魅力的です。また、適切な条件を満たすと、企業・従業員の双方に節税効果のあるものになります。
- 生活コストの削減に直結する食事や住宅関連の福利厚生は経済的インパクトがわかりやすい
- ランチ補助は、交流の機会創出にもつながり、チームビルディングとしても効果的
制度があっても、使われなければ意味がありません。大切なのは「その会社で働くメンバーが嬉しいかどうか」です。
独身が多いなら、アクセスの良いエリアへの家賃補助が効果的かもしれませんし、家庭を持つ社員が多いなら、育児や介護支援などを考える必要があります。
制度そのものも大事ですが、経営陣が『働きやすい環境をつくろう』という姿勢を示し、メンバーと対話をすることで、組織の透明性や信頼感を高めることができます。
- 年齢・家族構成・通勤手段などのデータを分析し、ニーズベースで制度を柔軟に見直そう
- 年1回の制度アンケートなど、社内からの“声”を拾う仕組みを組み込むと、満足度もアップ
- 「利用した人の声」を社内で共有することで、制度の活用促進と定着が図れる

成果・企業成長につながる仕組みを
スタートアップの多くは、スピード重視の体制ゆえに、明確な人材育成制度を整える余裕がないまま事業が進むことも少なくありません。だからこそ、学習機会を福利厚生として制度化することは、現場の成長意欲に応える有効なアプローチになります。
書籍購入や外部講座の費用補助は、成長意欲を持つ社員を後押しすることができます。
とはいえ、単にお金を出すだけでは使われないケースもあるので、評価制度と連動させるなど、仕組みとして設計することが大切です。
例えば、学びが成果にどうつながるかを見える化したり、社内勉強会やLT(ライトニングトーク)と組み合わせることで、インプットとアウトプットの循環を促すことができます。
福利厚生は一度きりの設計で終わるものではなく、社員の声をもとに継続的に見直していくことが大切です。
資金やリソースが限られていても、小さく始めて、仮説・実行・検証のサイクルを回すことができれば、制度はやがて組織の文化として定着し、働きやすさ・エンゲージメント・企業成長にまでつながる仕組みへと進化していくでしょう。
ON&BOARD TIMES編集部
ON&BOARD TIMES編集部